自律神経弱子の自律神経ばなし③【自律神経失調症 パニック障害】

おはようございます。
神戸元町の鍼灸院、摩耶はり灸院の畑綾乃です。
気温は上がりますが湿度は低め、気持ちいい日になりそうです。
***
自律神経の過敏性を鎮めて、症状が出ないようにするには、脳と体を休ませること、という話しを前回書きました。
難しいのは、脳を休ませること。
思考の量がポイントになります。
そうです、頭がいっぱいいっぱいになると、自律神経の緊張スイッチが入りやすくなる。
思考の中でも、ネガティブな思考というものは、堂々巡りになって思考が止まらなくなる種類のもの。
ネガティブ思考は、思考量が増えていくものなので、自律神経への負担は大きくなります。
それにプラスして、ネガティブ思考、つまり不安や心配、怒り、悲しみなどのことですけれども、そういう感情がわくということは、動物としてピンチなときなんです。
自分を守らなくちゃいけないので、ストレスの元と戦うために、体が頑張らなきゃいけない方向に向くんです。
そのために自律神経が緊張のスイッチが入りやすくなる。
脳の思考量と、ピンチな状況、この2つが、合わさって自律神経を刺激してしまう。
こういう仕組みがあるということを覚えておくと、ネガティブなことばかり考えてると、なんで調子が悪くなるのかな?
というのが理解していけると思います。
ネガティブな思考だらけの生活は、一つもいいことないですよ。
楽しいこと、ワクワクすることで思考がいっぱいになっても、自律神経はバーストしません。
だって、脳にたくさん元気になるホルモンが出るから。
元気ホルモン、楽しいホルモンは、自律神経をフォローしてくれる、自律神経を整えてくれるんです。
だから、脳の思考量が増えすぎないように、あれこれ考え過ぎないように、自分で工夫するのは大事だけれども、その思考の種類を選んでいくこともコツなんです。
あれがイヤだな、これがつまらないな、と生きているのと、ワハハと笑ってなんでも楽しんで生きるのとでは、自律神経を通して体に与えるインパクトがだいぶん違ってくるものなんです。
脳の思考量が増えてしまう、いくつかの例を次回も書きますね。
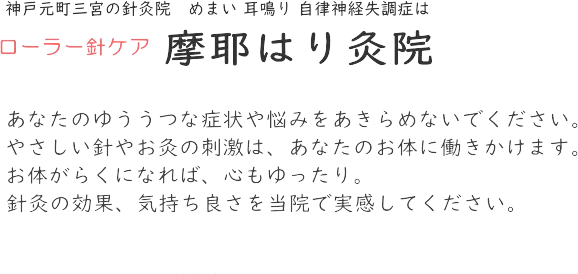




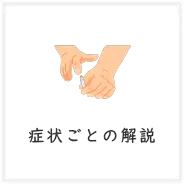








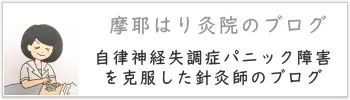





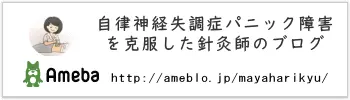
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません